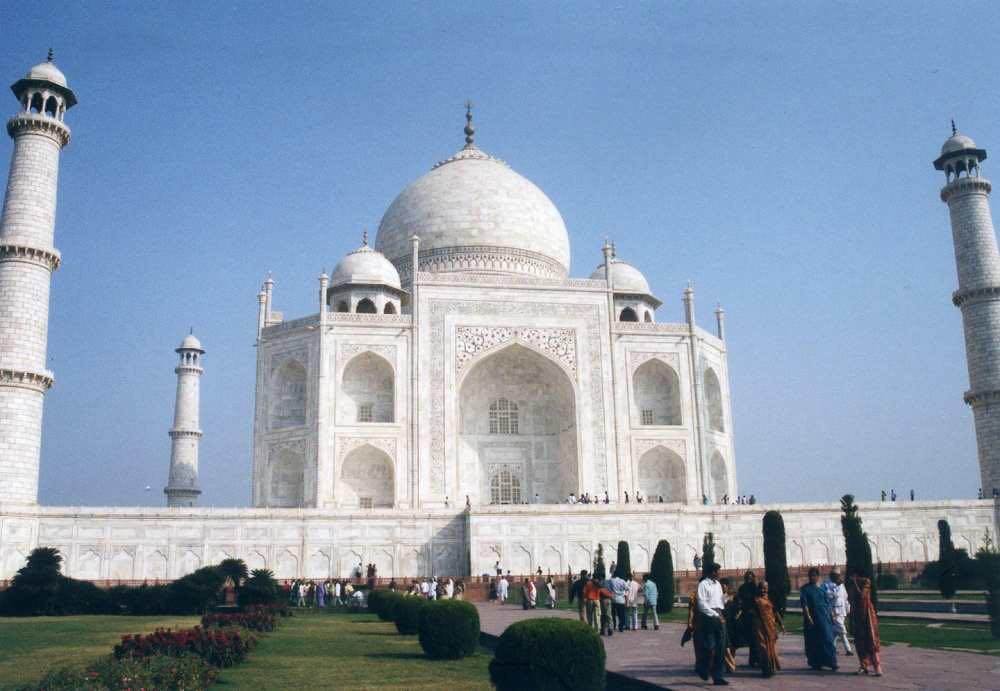コンサートホールを振動させるシタールの調べ
ヴィーンンン……。
タンプーラのうねるような音が辺りの張り詰めた空気を微かに振動させている。
嵐の前の静けさ。
東京、新宿オペラシティのだだっ広いコンサートホールの舞台は、スコールが降る直前のような重く濃厚な気配に包まれていた。
不意に稲光のような音の閃光が煌く。ゆっくりと聴こえてくる、キラキラと眩い、黄金のような旋律。
シタールである。
トゥン、トゥン、トゥトゥン……。
しばらくすると、その旋律に呼応したタブラが、まるでぽつぽつと降り始める夕立のような軽快なリズムを、始めはゆっくりと、そして、徐々にスピードを上げながら、叩き始める。
ドゥドゥドゥン、ドゥドゥン……。
それを厳かに伴奏するバヤンの、雷鳴のように深く、くぐもった音。
ラーガが始まったのだ!
うねるように続く心地よい反復。麻薬のように沁み入ってくるその音世界に身を委ねていると、いつしか心は広大なインドの原野に誘われてゆく。
淡い乳白色の靄に包まれた平原。疎らに生えた菩提樹が地平線の向こうまで延々と続いている。悠然と立ち尽くすこぶ牛、裸で遊び回る子供たちの群れ。空には小鳥がさえずり、大地には頭に壺を載せたサリー姿の女性が背筋を伸ばしながらゆったりと歩いているのが見える。
歴史とか時間とか、そんなものを超越した悠久の風景。インドの風景だ。
壮大な音の洪水に圧倒され、オペラシティの聴衆は水を打ったように静まり返っていた。
人々はまるで、シタールとタブラが紡ぎ出す催眠術にかかってしまっているかのように、目の前の舞台を突き抜けた何万キロも彼方にある幻想のインド風景を、目を細めながら眺め続けていた。

日本のコンサートホールで、そして、我が家でCDをかけて、私は幾度となくインド音楽の音色を聴いた。
インド音楽の深く重く煌びやかなサリーの色合いのような旋律や、まるで魔術のような手から繰り出される、複雑で、そして、単純なリズムに私はいつでも恍惚とさせられてしまう。
インドに来たからには、名演奏家の、本場の、現地の、生の演奏を是非とも聴いてみたいものだと私は思っていた。
だが、それは想像以上に難しいものだった。
私はいくつかの街で、文化会館のホールを訪れ公演のスケジュールを見たり、観光局へ行き演奏会が開かれていないか尋ねたりした。
しかし、やっていなかった。
ちょうどコンサートのない時期にインドを訪れてしまっていたのか、それとも、私の情報収集が甘かっただけなのか……。
結局、現在に至るまで、私は本場インドでの熱狂に包まれたコンサートを体験することが出来ないでいる。残念なことだ。
ところが、デリーに滞在中、デリーの下町、それも、パハール・ガンジの路地裏で、私は思いもかけず、シタールとタブラのささやかな演奏を聴くことが出来たのである。
それも毎日のように。
パハール・ガンジの路地裏のシタール弾きおやじ

パハール・ガンジから横に入った小道。
絡み合った電線が蜘蛛の巣のように覆っている狭い路地の暗がりの中には、薄汚れたネオンサインがぼんやりと浮かび上がっているのが見える。
そんな場末を思わせる一角にホテル・ダウンタウンはあった。
垢抜けない雰囲気の宿の受付には2人のおやじがいつも交替で座っていた。
親戚同志だという2人はあまり仲が良くないようで、ことあるごとにお互いの悪口を言っていたものだった。
そのうちの1人が、そう、シタール弾きだったのである。
彼は私がインド音楽に興味があるということを知ると、
「うちにシタールを聴きに来ないか?」 と熱心に誘ってきた。
彼の家はホテルから歩いて10分ほど。網の目のように入り組んだパハール・ガンジの裏路地をくねくねと行ったところにあった。
外国人の姿など1人もない裏路地の未舗装の通りには泥まみれの鶏がコッコッと走り回り、これまた泥まみれの豚がブイブイと地面をまさぐっている。
バン!と木戸を開け、子供たちが飛び出してきて、「ハロウ!ハロウ!」と飛び切りのニコニコ顔で挨拶してくる。
おやじの家は日本の農家のような雰囲気があった。
中庭を囲んで一階建ての質素な建物が三つ取り囲んでいる。中心には井戸があり、洗い場があり、豆の殻を剥いている老婆の姿があった。
おやじの部屋は狭かった。ぼんやりとオレンジ色の裸電球が内部を照らし出している。ベッドが部屋の半分を占領しており、壁には神棚やら、神様の絵やら、シタールの先生らしき人の写真やら、いろんな物がごちゃごちゃと飾られていた。
彼が言った。
「プリーズ、シッダウン!」
布の敷き詰められた土間に私は胡座をかいて座った。
「チャイを飲むか?」
おやじが訊いてくる。
「飲む」と答えるとおやじは、
「*****!」と大声で叫んだ。
すぐに赤いパンジャビードレス姿の可愛らしい娘さんがチャイを2つ、持ってきた。
「ナマステー(こんにちは)」
私が挨拶すると彼女ははにかみながら「ナマステ」と答えてくれた。
彼女が去った後、熱くて甘いチャイを啜りながら私はおやじに訊いた。
「彼女はあなたの娘さん?」
おやじが答える。
「いいや、違う。使用人だ」
恐らく私の視線の動きを目敏く感じ取っていたのだろう。おやじはこう続けた。
「だけど、彼女には旦那がいる」
余計なお世話だ。と私は思った。
チャイを飲み終えるとおやじはベッドの下からおもむろにシタールを取り出した。
ヴィヨーン、ヴィヨヨヨーン……。
チューニングを始める。
弦を引っ張りながらおやじが話し掛けてきた。
「毎日、夕方の五時にここに来ればシタールを教えてやってもいい。お金はいらないよ。私は日本人が大好きだから」
不意におやじは立ち上がると、棚から一枚の手紙を取り出した。
それを開いて私に見せる。そこにはわかりやすい英語で短い文章が書かれていた。
そして、写真が一枚、挟んであった。写真にはおやじと並んで女性が写っている。
手紙の文末には「From Yumiko(仮名)」とある。日本人女性からの手紙だ。
「この日本人女性。私は彼女に三ヶ月、シタールを教えてやったんだ。もちろんお金は取らなかったよ」
そして、私の目を覗き込みながらこう言った。
「だけど、彼女は日本に戻った時、私に時計を贈ってくれたよ。日本製のいい時計だ」
おやじは腕を見せた。そこにはセイコーの結構高価そうな時計がキラキラと輝いていた。
日々繰り返されたおやじとの戦い

結局、私はこのおやじに2週間近くシタールを習った。
しかし、その間、やはりと言うべきか、案の定と言うべきか、毎日のように物をねだられることになった。
メモを取るためボールペンを出すと、そのボールペンをくれと言われる。
東急ハンズで買った筆入れを目敏く見つけると、自分のボロボロのペンケースと交換してくれと言う。
「何かいらないものは持っていないか?あったらくれ」と言う。ずうずうしい奴だ。
私は仕方なく、日本から持参した煎餅を彼にプレゼントした。
しかし、そんな物で満足させられるはずはないということはわかっていた。何しろリッチなセイコー時計を貰っているのだ。
日本人はいい物をくれるものと期待しているのである。
そのうちおやじは自分の欲しい物をいろいろと列挙し始めた。
ウォークマンが欲しい、ラジカセが欲しい、キーボードが欲しい……。
とりわけキーボードが欲しくて堪らないらしく、こういう形でこういう機能が付いている物、と細かく指定してくる。
クリスマスの日の子供にでもなったつもりなのだろうか。もう貰う気まんまんだ。
私は思った。「そろそろ釘を刺しておいた方が良さそうだぞ」
私は言った。
「残念ながら私はそんな高価な物を買えそうにないよ。旅行で金を使ってしまうから日本に帰ったら貧乏なんだ。日本は給料が高い代わりに物価も高い。私が何かで成功してリッチマンになったらそういう物をプレゼント出来るけど、すぐには無理だよ」
それを聞いて明らかに不機嫌になるおやじ。
しかし、折角捕まえた金づるである。簡単に手放すわけにはいかないようだ。
おやじは作戦を変えた!泣き落としである。
眉間にしわを寄せ、悲しそうな表情でぶつぶつと呟き始めるおやじ。
うちは家族が多いから生活が苦しいだの、ホテルの受付の仕事だけじゃ好きな物も買えやしないだの、今日は昼飯抜きだっただの、妹の誕生日プレゼントを買ってやりたいのだが金がないだの、延々と訴え始めた。
それを、ふんふんと聞き、「わかるよ」と相槌を打ちながらも私は冷徹にこう答えた。
「あなたの窮状はよくわかった。けど、あなたにキーボードをプレゼントをすることはできない」
おやじはそれを聞くと憮然と押し黙ってしまう。
彼の家に行く度にそういったやりとりが繰り返された。
初めは鬱陶しくないこともなかったが、そのうち慣れてしまった。
「また、始まった!」という感じである。
しかし、そのうち彼も、どうやらこれは無理そうだと判断したらしい。次第におねだりも泣き落としもなくなっていった。
そして、それと共にシタールの教授もおざなりになっていった。
結局、私は12日間でおやじによるシタールの受講を打ち切った。 ただでいいとは言っていたが、私は受講料として200ルピーを支払った。
特別有難がっているというわけではないようだが、その表情からはある程度満足しているということが窺えた。
黄金のように煌びやかな音色を奏でるおやじのシタール

インドの音楽家は『音により梵我一如を追求する』といわれるインド世界においてはとても尊敬される存在である。
おやじのおねだり攻撃はそんな音楽家の風情とはかけ離れたものであった。
しかし、ひとたびシタールの弦を弾き始めると、その姿はまるで、泰然自若とし人生を悟りきった哲学者のような風貌に変わるのだ。
恥ずかしげもないおねだりや泣き落とし、ぐるぐると渦巻いている欲望なんかはどこかへと吹き飛んでしまうかのようである。
おやじの紡ぎ出すこの素晴らしい音色は、辺りの空気をピーンと緊張させ、それでいて、聴く者を柔らかく包み込むような安らぎを与える。
私はいつでも、おやじのシタールの音色を聴くだけで、彼を尊敬する気持ちになってしまうのだった。
黄金のように煌びやかな音色を奏でるおやじのシタール。
彼の脇では、義理の弟がマシンガンのように目にも止まらぬ速さでタブラを叩き続けている。
2人の奏でるささやかだが熱っぽい演奏を聴きながら、私の心はまた、広大なインドの原野に誘われていく。
デリーの、パハール・ガンジの路地裏の、狭苦しく薄暗い部屋。
そこには悠久のインドの茫漠たる大平原がどこまでもどこまでも広がっているのが見えた。
旅行時期:2003年10月
続きの記事・関連記事
続きの記事
関連記事